
|


 ▲池田卓夫氏
▲池田卓夫氏
日本経済新聞社編集委員
|
|

|
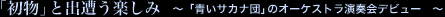

今年7月末から8月初めの1週間、チェンバロ奏者の中野振一郎の旧東独地域リサイタル・ツアーに独語通訳というか添乗員まがいの世話係というか、とにかく同行した。J・S・バッハがアイゼナハ、ヘンデルがハレ、テレマンがマグデブルク、シューマンがライプツィヒ……と、旧東独には旧西独に比しても多く、大作曲家の生誕地が集中する。そこで日本人がバッハを弾くこと自体、大きな挑戦と言えるが、ドイツの聴衆は個々の演奏家より音楽、作品そのものに関心を寄せるので、中野の登場にも奇異の目ではなく、温かな眼差しが向けられた。辛口の音楽批評でも知られるという若いドレスデンの作曲家、アレクサンダー・コイクは地元紙「ドレスナー・ノイエステ・ナッハリヒテン」で「未知の状態で素のまま音楽に接するのは、いつも際立って興味深い。一人の芸術家との音楽のであいの第一歩は、長く印象に残るものだ」と書き出した上、中野との遭遇を「とりわけポジティブ」と評し、「その演奏は美しく、つよく、真の"耳のご馳走"だった」と絶賛した。
|
人口の4、5人に1人が失業者という旧東独地域に比べれば、日本は、はるかに豊かな国で、世界有数の歌劇場やオーケストラ、独奏者などの来演、国内演奏家の公演を切れ目無く楽しんでいる半面、一つの作品、一人の演奏家、一夜の演奏会との出遭いをそれほど真剣には受け止めていない。公演の大半は音楽事務所に仕切られ、イベントとして産業化される一方、聴衆もグッチやエルメスなどのブランド商品を買い漁るかのように、音楽市場で知名度を確立した演奏家が提供する2時間なり3時間に大金を投じ、消費していく。アフターのディナーでも良くて解釈の善し悪し、最悪だと演奏家の服の趣味や容姿ばかり話題に上り、作曲家独自の様式や創作の軌跡、作品を生んだ社会や文化圏、時代、テキスト(歌詞)の内容などから、自分が一人の「生きる存在」として何を得たかといったテーマは敬遠されるか、全く眼中にない。音楽にまで飽食した日本人の内面は、お寒い限りだ。
前置きを長く書いたのには、理由がある。まず今夜、神田慶一指揮「青いサカナ」管弦楽団(Orchestre du Poisson Bleu)として初めてのオーケストラ演奏会に足を運んで下さったこと自体、日本の聴衆として飛び抜けて勇敢な判断を下したことになる、と持ち上げたいと思ったからだ。国立音楽大学のオペラ好きの学生たちがわいわいがやがやとカンパニーを立ち上げてから15年、青いサカナ団は一貫して歌劇の上演団体であり続けた。神田が作曲家、指揮者としての経験を深め、それぞれの上演も専門家から一定の評価を受けるようになったとはいえ、二期会や藤原歌劇団、あるいは新国立劇場に比べれば、まだ知る人ぞ知る存在。カウンターカルチャー、サブカルチャー、オフ・オフ・ブロードウェー、お洒落なブティック……。何とでも例えられるが、とにかく、メジャーではないところの魅力を放っている段階である。ましてシンフォニー演奏の力量は、全くの未知数と言える。
作曲家としての神田はクラシック、ロックなどの分類を超え、豊富な音楽語法の引き出しを持っている。指揮する作品の選択においては、決まりきった「型」が支配する古典よりも、それが崩れ行く過程に咲いた音楽の色香への志向が強いようで、作曲上の調性ばかりか欧州の秩序までが破壊された時期、19世紀末から20世紀の半ばにかけての近代作品を主に手がけてきた。グスタフ・マーラー(1860−1911)の「交響曲第1番」は1888年3月にライプツィヒで完成、89年11月にブダペストで作曲者自身の指揮で初演。モーリス・ラヴェル(1875−1937)の「ピアノ協奏曲(両手)」は1931年11月に完成、曲を捧げられたマルグリット・ロンの独奏、作曲者指揮のコンセール・ラムルー管弦楽団による世界初演は32年1月のパリ。リヒャルト・シュトラウス(1864−1949)の「四つの最後の歌」は死の前年、1948年5月から9月にかけて作曲されたが、初演は作曲家の死後、50年5月のロンドンで、キルステン・フラグスタート(ソプラノ)の独唱、ヴィルヘルム・フルトヴェングラー指揮フィルハーモニア管弦楽団の管弦楽という豪華な布陣で実現した。
3人の作曲家は没年こそ第一次世界大戦前夜、第二次世界大戦前夜、第二次世界大戦後とまちまちだが、生年は19世紀後半の15年間に重なっている。ほぼ同じ時代に生を授かりながら、個の特質だけでなく、それを超えた時代、社会の流れに巻き込まれ、かなり傾向を異にする作曲家としての人生を終えた。だがマーラーとシュトラウスには生前、オペラ指揮者として活躍した共通点がある。シュトラウスのモーツァルト解釈には定評があり、カール・ベームら指揮の弟子に大きな影響を与えたし、ラヴェルの協奏曲の第2楽章からはモーツァルトのピアノ協奏曲のエコーが聴こえてくる。三つの作品の背景を探るとき、ロマンティシズム、モダニズムの底に、実は「古典」の大きな根幹を感じることができる。
例えばマーラー。交響曲という様式の起源には諸説あるが、最終的にウィーン古典派のフランツ・ヨーゼフ・ハイドン(1732−1809)が完成したとの見方では一致している。起承転結を体現した4楽章の構成とともに、主題の調性がはっきりと提示される。ハ長調なら「明るく」、ニ長調なら「祝典的に堂々と」、ト短調なら「不安にかられ」……と、何かにつけ型を重視した18世紀の音楽では、調ごとのキャラクターも明確に規定されていた。19世紀も半ばを過ぎたロマン派音楽の爛熟期、作曲家自身の心情吐露と古典的な様式感との食い違いが拡大すると、交響曲の形式を崩し、調性の束縛から逃れたいとのエネルギーも高まりをみせた。20代半ばの青年作曲家マーラーも最初の交響曲を構想した時点で、楽章数を4から5に増やし、それぞれに標題を付けてみた。初演で満足な評価を得られなかった結果、伝統的な4楽章形式に戻り、標題を撤回する形で現行版の状態に落ち着いた。
マーラーのハイドンに対する敗北という見方もできるが、ここでは、ニ長調の肯定的な性格をフルに引き出し、決然と第一歩を踏み出した青年の強烈な自己主張のフィナーレと受け止めたい。21世紀初頭に生きる私たちは、マーラーが最後に完成(1910)した「交響曲第9番」の調性が再び、ニ長調であることを知っている。瞑想的な主要主題が何度も繰り返され、消え入るように終わる「第9番」の最終楽章を無調音楽への予感と関連付けて語る例は多いが、4楽章構成、二長調に回帰した事実を重視した時、マーラーの心に映ったのは崩壊への怖れではなく、自らの生が消えた後に現れる新しい世界への希望だったように思える。それからさらに1世紀後、私たちが神田とサカナ団の奏でる「マーラーのニ長調」に素の状態で接し、得られるものもまた、明日への希望であって欲しい。(了)

|



|

|

